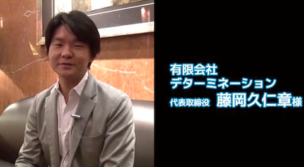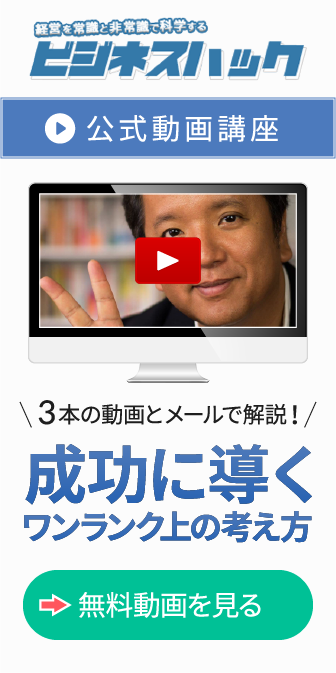絶対理解しておきたい!退職手続きのポイントと注意点とは?

「仕事が楽しくない」
「新しい仕事を始めたい」
人によってそれぞれ理由は違いますが、現状の仕事に満足していない場合、退職を考えることもあるでしょう…。
しかし、いざ退職を決めて退職手続きを行うときには、注意しておくべきことがあるのをご存知でしょうか。
ただ退職届けを出して辞めればいいという訳にはいかないのです…。
Contents
退職手続きのポイント
退職手続きを行う前に、まず会社を辞めるタイミングを考えましょう。
- 「転職が決まっている場合」
- 「退職してから転職活動or起業」
によって、退職するタイミングは変わってきます。
転職が決まっている場合
転職が決まっている場合は、転職先と入社日から逆算して退職日を決めてください。
ほとんどの会社は
「今すぐ辞められるのは困る。」
「次のスタッフが入るまでもう少し待って欲しい。」
などの退職日程の交渉を行ってきますので、退職までの日程が長引いてしまうことが多くあります。
最低でも転職先の入社日の前日までに退職しておかないと、せっかくの転職ができなくなってしまいます。
基本的に退職の1ヶ月~2ヶ月までに退職する意思を伝えるべきでしょう。
働けない期間を作らないためにも、やはり理想は転職の前日に退職することです。
何もしていない期間が長くなるほど、給料はもらえず支払いが多くなってしまうものです。
退職してから転職活動or起業の場合
退職してから転職活動、もしくは起業する場合には、賞与・有給を考えて退職しましょう。
社内規則にもよりますが、業績→査定→賞与という流れでもらえるため、一定期間が空いてから支給されるのが原則です。
そのため、退職手続きを行うなら査定が終わってからでないと、給与額が下がってしまいます。
辞めるとわかっている人に、将来の成長も含めた給与は頂けないでしょう。
また、有給は就業期間に合わせて支給されるものです。
参考 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
半年から1年経過するごとに有給日数が増えていき、最大で年間20日の有給になることがほとんどです。
少し待てば有給日数が増えるのなら、有給が確定してから退職手続きを行ってください。
有給をもらった後からは、好きなタイミングで有給消化ができますので、転職・起業の活動時間に充てられます。
効率良く退職するために、退職するタイミングは考えておいてください。
退職するときの注意点
さて、それでは退職するときの注意点を確認していきましょう。
今回は、退職する側の注意点と会社側の注意点を紹介しますので、ポイントを押さえておいてください。
どちらにとっても円満な退職を迎えられるように、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
退職する側の注意点
有給休暇と引き継ぎ
退職する側の注意点としては、退職手続きを伝えてからは確認事項を消化していきましょう。
取得した有給を消化するのはもちろん、仕事の引き継ぎをスムーズに行ってください。
円満な退職を目指すのなら、しっかりと同僚や上司へ相談することが大切です。
もちろん取引先へ挨拶周りすることも、大切な引き継ぎ業務の一つです。
有給消化に入ること、もしくは有給消化日を退職日として伝えておくようにしてください。
そうしておかないと、取引先・会社の対応が遅れてしまうので、迷惑をかけてしまいます。
また、有給を確定させたのなら、今ある有給日数を確認してください。
せっかく取得した有給ですから、消化してしまわないともったいないです。
例えば、15日間の有給を取得していて、16日から30日まで有給を申請したとします。
確かに有給を消化できているように見えますが、これはNGな使い方です。
週休2日制の会社なら、土日は有給として消化することはできません。
有給を消化できたとしても、11日分しか消化ができなくなってしまいます。
土日を計算に入れてしまうと、有給が消化されなくなってしまうため、しっかりと日数を確認しておきましょう。
手続き関係
さらに、会社を退職した後には、ハローワークに行かなければなりません。
失業保険を給付してもらう手続きで、
- 離職票2枚
- 写真2枚
- 身分証明書
- 預金通帳
- マイナンバー
- 印鑑
等が必要になります。
※詳細は最寄りのハローワークに問い合わせてください
ちなみに、退職したからと言って、すぐに手続きを行えるわけではありません。
離職票2枚は会社からもらえるのですが、会社がハローワークで手続きを行わないと、もらうことができません。
そのため、会社から離職票を送ってもらわないと、手続きはできません。
あまりにも離職票が届かない場合には、会社に連絡をした上で、できる限り早く離職届けをもらうようにしてください。
自己都合で退職した場合には、3ヶ月の給付制限が掛かりますので、手続きが終了しから3ヶ月は失業給付金が受け取れません。
そして失業保険を受けとるためには、就職活動を行う必要があります。
転職・起業を考えて自分で行動している場合、失業保険の日数はカウントされません。
それぞれルールがありますので、事前に確認しておきましょう。
ハローワーク所在地案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068159.html
会社側の注意点
会社側は退職者が出てくると、さまざまな手続きをしなければいけません。
退職届を提出してもらい、雇用保険被保険者離職証明書の内容を確認してください。
- 健康保険継続の確認
- 住民税徴収方法の変更
- 貸与品回収
など、さまざまな手続きを行わなければなりません。
あらゆる手続きと同時に、円満な退職のために対応をしていく必要があります。
退職をせずに続けてもらえるよう、ある程度の退職交渉を行うことになるでしょう。
しかし、過度な交渉をしてしまっては、トラブルの元になりかねません。
納得が行くように円滑な交渉を行ってあげてください。
手続き関係
各書類に記入・署名・捺印をしてもらい、すばやく各機関に提出する必要があります。
そのためには、なぜこの書類が必要なのか?サインするのか?をわかりやすく説明してあげてください。
何の処理を行っているのかわからないと、退職者も不安に感じてしまうものです。
ハローワークに資格喪失・離職証明書を提出しなければいけませんし、退職者に書類の受け通り日を伝えて、スムーズな手続きをしなければなりません。
所得税の手続きもあるので、源泉徴収票を作成して1ヶ月以内に退職者へ渡す必要があります。
退職証明書の発行
労働基準法を守るために、退職証明書を作成しなければなりません。
都合良く処理してしまわないように、退職者の請求していない項目は請求すべきではないです。
-
労働基準法第22条
- 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
- 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
- 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
- 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない
まとめ
スムーズな退職を行うためには、退職者側も会社側もどちらも円満に解決できるようトラブルを起こすべきではありません。
退職でモメてしまうと、ムダな時間と労力が掛かってしまうようになるでしょう。
また、すべての手続きを円滑に進めて行くことで、的確に処理が進んでいきます。
退職者であればこれから先の仕事を、会社は新しい人材の育成を、将来を思って進んでいくのがベストです。
円満な退職のために、注意点を押さえて過ごしていきましょう。
「退職は手続きが面倒」
「すっきりと辞められたらなぁ」
と考える人も多いかと思いますが、退職者であっても会社側であっても、スムーズに退職するなら注意点を押さえて、協力しながら手続きを進めることが大切です。
相手のことを考えた上で適切な対応を取っていけば、何もトラブルが起きることはありません。
どちらにとっても納得の退職手続きを行い、次のステップに気持ちよく進むことで、お互い更なる成長につながるのではないでしょうか。