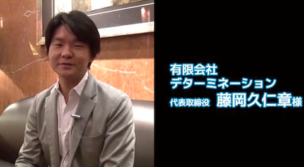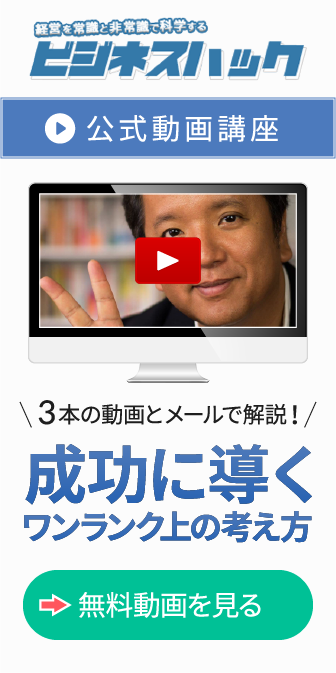知らないと損する!法人消費税の免除・納付・仕訳の方法

「会社を設立」したり「個人事業主から法人成り」したりすると、様々なことが必要となります。
その1つが「消費税」を納める必要があることです。
消費税は消費者個人が負担はしますが、法人が納付者になるからです。
しかし会社を設立したばかりだと「消費税の納付」と言われてもピンと来ないかもしれません。
また個人事業主から「法人成り」した人は、「法人成りすれば消費税の免除が受けられると聞いたけれどどんな条件なのだろう」と疑問に思っているかもしれません。
自分自身も普段は消費者なので消費税は身近なものではありますが、「仕組み自体は複雑なのであまりよく知らない」という方も多いのです。
そこで、
- 「そもそも消費税とは何か?」
- 「免除になる条件」「免除になる方法」
- 「消費税の計算方法」
- 「納付の仕方」
- 「経理処理の仕方」
など知っているようで知らない消費税について説明したいと思います。
この機会に「消費税について知りたい」方は、お役立てください。
「会社設立」・「法人成り」をした場合の消費税とは?
起業して会社設立すると「一国一城あるじ」になった気がして気分がよいものです。
しかしその分、責任も重くなる部分もあります。
社会人だった時には、給料から源泉徴収して年末調整して税金を納めていたけれど、自分で決算書を作成・税金を納める立場になります。
これは所得に対して話ですが、消費税の対する立場も変わります。
消費者の場合は買い物をした時に消費税を負担しますが、あくまでお店に払うだけでした。
しかし法人となれば、その消費者から預かった消費税を納付する立場に立つのです。
そこで「消費税って何だろう?」とか「どのように納めるのだろう?」と疑問に思う方も多いはずです。
また「法人成り」した場合も同様です。
「法人成り」とは、今まで個人事業主として事業を行っていた人が法人を設立することです。
すでに事業をしてきているので確定申告などをしているでしょうし、場合によっては消費税も納めているかもしれません。
この場合は全く初めて法人設立する場合とは少し違いますが消費税と言う点では疑問も多いかもしれません。
そもそも「消費税」とは?
では、「そもそも消費税とは何か?」と言うと「消費者が物の購入やサービスの提供を受けた時に納める税金の事」です。
日本の場合は基本的には間接税となっており、消費者が税金を負担しそれを預かった事業主が納税することになります。
また間接税と言うと特定の物やサービスに課税される個別間接税もありますが、消費税は特定の物やサービスを対象ではなく広く消費を対象にしています。
なお個別間接税としては、
- 酒税
- たばこ税
- 揮発油税(ガソリンなどに対する税金)
があります。
日本では個別間接税はかなり以前からありましたが、消費税は1989年(平成元年)の税制改正で新設されたものです。
この当時は、消費税は3パーセントからのスタートでした。
その後1997年(平成9年)に消費税が3パーセントから5パーセントに増税されました。
さらに2014年(平成26年)には5パーセントから8パーセントへ増税されています。
このように消費税は日本でも平成に入ってから導入され、徐々に増税されてい間接税の1つなのです。
「消費税」は誰が納めるのか?
所得税などは所得がある人が所得額に応じて払うのですが、消費税は所得に関係なく消費したものに対して公平に払うという仕組みです。
所得の高い大人が購入した場合でも、所得のない子供が購入した場合でも消費税は同じ率で掛かり負担することになります。
消費税は間接税ですので消費者が払ったものを事業者(法人など)が預かって、納税することになります。
会社成立したり法人成りしたりすると消費税の納税義務が発生することになるのです。(個人事業主でも金額によっては対象になります。)
消費税の増税の時期と影響とは?
次に「消費税が10パーセントになる」と言う話があります。
この時期はいつなのでしょうか?
消費税はでは、1989年(平成元年)新設された当初は3パーセントでした。今まで消費税が無かった日本では大反対が起きましたし、消費者も事業者も大混乱をしたものです。
その後1997年(平成9年)に消費税が3パーセントから5パーセントに増税された時にも、一部混乱が起きました。
消費税込みの総額を表示することが基本となり、値段の書き換えなど大変な作業を強いられた事業者も多くありました。
さらに2014年(平成26年)には5パーセントから8パーセントへ増税されています。
ここのあたりから消費者も慣れてきたのかあまり混乱が少なく、事業者も総額表示だけでなく税別表示も許されるようになり混乱が少なくなりました。
次に8パーセントから10パーセントへの増税も予定されています。
当初2017年(平成29年)4月1日に増税予定でしたが、2019年10月1日に延期されています。
このように消費税は増税や制度の変更もあり、納税者である法人はそれらについても知っておく必要があるのです。
法人化するメリットは?
法人化する(会社設立したり、法人成りしたりする)と、消費税など面倒くさい問題が増えてきます。
しかし法人化するメリットもあります。
例えば、
- 法人との取引しかしない企業とも取引が可能になる(信用力アップにつながる)。
- 所得が一定以上になると個人事業主より税制が有利になる。
- 退職金を設定できる
- 決算日を自由に変更できる(個人事業主は基本12月31日が決算日)。
などがあります。
そして今回のテーマでもある消費税についてもメリットがあります。
会社設立後2年間または法人成り後2年間は、消費税の免税事業主になる可能性があります。
消費税の納付方法と免除を受けるには?
原則課税と簡易課税とは何か?
消費税の課税の仕方として、
- 「原則課税」
- 「簡易課税」
と言う2つの方法があります。
文字の通り「原則課税」が原則的な方法であり、通常はこちらで課税されます。
しかし原則課税は計算方法も複雑であるので、中小事業者には「簡易課税」(原則課税より簡易な方法)を選択することが出来ます。
ここで対象となる中小事業者とは、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下の企業のことになります。
「原則課税」が基本なので、「簡易課税」を選択するのであれば、先に届出書を税務署に提出する必要があります。
消費税の計算方法
では「原則課税」と「簡易課税」のそれぞれの場合の計算方法を見ていきましょう。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の企業であれば、有利な計算方法を選べるからです。
原則課税
まず「原則課税」です。
原則の方法なので、「消費者などから預かった消費税-仕入れなどで支払った消費税」で計算します。
もう少し分かりやすく計算式にまとめると
「売上高×消費税率―仕入高×消費税」
となります。
例えば、消費税が8パーセントして、600円で仕入れたものを1,000円で売った場合
「1,000円×0.08-600円×0.08=32円」
となります。
簡易課税
次に「簡易課税」の場合です。
簡易課税の場合は、支払った消費税を把握はしません。
どのように計算するかと言うと、預かった消費税に「みなし仕入れ率」と言う一定割合をかけて納税額を計算します。
分かりやすく計算式をまとめると
「売上高×消費税率―売上高×消費税×みなし仕入れ率」
となります。
みなし仕入れ率は事業の区分によって違います。以下のようになっています。
| 第一種事業(卸売業) | 90パーセント |
| 第二種事業(小売業) | 80パーセント |
| 第三種事業(製造業等) | 70パーセント |
| 第四種事業(その他の事業) | 60パーセント |
| 第五種事業(サービス業等) | 50パーセント |
| 第六種事業(不動産業) | 40パーセント |
例えば、消費税が8パーセント、小売業にて1,000円で売った場合(小売業の場合、みなし仕入れ率は80パーセントなので・・・)
「1,000円×0.08-1,000円×0.08×0.8=16円」
となります。
上記の例で見ると両者とも単純化しているのでどちらでも作業は同じように見えますが、「原則課税」の方が
- 「預かった消費税」
- 「支払った消費税」
すべて帳簿につけて管理することになるので事務処理が大変になります。
逆を見れば「簡易課税」の方が「預かった消費税」だけを把握しておけばよいので事務処理が楽になり、課税売上高5,000万円以下の場合にはこちらも選択できるのです。
事務処理は「簡易課税」の方が有利になりますが、計算した場合どちらが得かは別の話になります。
上記の例ですと
- 「原則課税が32円」
- 「簡易課税が16円」
となっており簡易課税が得になっていますが、いつもこうとは限りません。
例えば、サービス業で売上1,000円に対して600円仕入れだとします。(消費税は8パーセントで計算)
原則課税では「1,000円×0.08-600円×0.08=32円」
簡易課税では「1,000円×0.08-1000円×0.08×0.5=40円」
となります。
この場合ですと、原則課税の方がお得になります。
しかし前述のように原則は「原則課税」であり、「簡易課税」を選択する際には、「消費税簡易課税制度選択届出書」と言う届出書を先に提出する必要があります。
つまり後から「こっちのほうが良かった」と選択を変えることはできませんので、注意が必要です。
「消費税の納付」の方法とは?
個人事業主の場合は、事業年度が12月31日までで3月15日までに「確定申告」を行いますが、「消費税の申告、納付は3月31日まで」となりますので注意が必要です。
法人化(法人設立・法人成り)の場合は、決算日を自分で決めることが出来ますので、決算日から2カ月以内が期限となっています。
なお申告期限の延長は認められていませんので注意が必要です。
もし消費税の申告・納付をしなかったら(遅れたら)どうなのでしょうか?
納付が遅れた分の延滞税を取られます。
算定方法は法定の納付期限の翌日から完納日までの日数に応じての延滞金となります。
さらに納付しないと差し押さえなどの強制的な手段を取られる場合もありますので注意が必要です。
決算後急に消費税額すべてを支払うというのは、売上規模が大きくなればなるほど厳しくなります。
消費税は
- 中間申告
- 中間納付
と言う仕組みがあります。
前年(前期)の消費税額に応じて年度の途中に申告、納付することになります。
しかしここで中間申告・中間納付が不要な企業もあります。
中間申告・中間納付は消費税の国税分が48万円以下なら不要となるのです。
逆に言えば48万円以上であれば、すべての企業が中間申告・中間納付が必要とも言えます。
年に何回するのかと言う回数ですが金額が多いほど、中間申告・中間納付の回数は多くなります。
なお48万円以上400万円以下であれば、年1回の中間申告・中間納付になります。
例えば前年(前期)消費税額が100万円であれば、50万円分先に中間納付するということです。
「消費税を免除」できる条件とは?
消費税の免除が受けられるかどうかは、企業にとって(資金繰りにとって)重要です。
消費税の免除の判定基準は資本金1,000万円未満の企業であり、2年前(2期前)の売上が1,000万円を超えたかどうかです。
つまり法人化したばかりであれば、2年前の売上は1,000万円ありませんので、消費税も免除になります。
注意が必要なのは以前は2年前(2期前)の基準のみだったので2期目も免除になったのですが、現状はその制度は変更されています。
2013年(平成25年)からは2期目は直前期の上半期で1,000万円超えていると免除になりませんので注意が必要です。
逆に言えばこの基準をクリアしていれば、2年間は消費税が免除になるというメリットがあります。
いきなり法人化した場合でも免除はメリットとなりますが、個人事業主をしていて1,000万円を超える状況であれば、法人化(法人成り)するメリットは大きいのです。
消費税の経理処理とは?
中間申告・中間納付があったり計算方法も選択できたりしますので、消費税の経理処理を迷う方もいると思います。
ベテランの経理の方や税理士に依頼できるのであれば問題ありませんが創業したばかりの頃は
- 経営者自身が経理処理する
- 親族(奥さんなど)が経理処理する
など慣れていないこともあります。
「消費税」と「決算」
「消費税」は決算を行って計算・申告し、納税を行います。
決算日がいつかと言う点は大きく影響していきます。
個人事業主であれば決算期間は1月1日~12月31日なので、決算日は自動的に12月31日になります。
そして確定申告が3月15日までになりますが、消費税は3月31日までの申告・納税になります。
これも土日などによって数日の差はありますが、すべての個人事業主は統一されています。
それに比べて法人化すると決算日より2カ月以内となります。
消費税の申告・納付としては個人事業主の場合に比べて短くなっているというデメリットはあります。
しかし法人の場合は決算日を自由に設定できます。
例えば3月に申告や納税をすると年度末で繁忙期に重なり大変であれば、5月決算・7月申告、納付と言うことも出来るのです。
消費税の話だけで決算日を決めるわけではないですが、法人税の申告も同時期になりますので、決算処理の時期によって決算日を決める企業も多いのです。
消費税の経理処理とは?
消費税の経理処理には、
- 税抜きでやる場合
- 税込みでやる場合
があります。
消費税額としては変わりませんが収益の金額は変わります。
具体例で見てみましょう。
事例
商品5,000円(税込み5,400円)を仕入れものを、10,000円(税込み10,800円)で売り上げた時の経理処理です。
<税抜き処理の場合>
- 仕入れ時の仕訳
(借方)仕 入 5,000 / (貸方) 現金 5,400
仮払消費税 400
- 販売時の仕訳
(借方)現金 10,800 / (貸方) 売 上 10,000
仮受消費税 800
- 決算(消費税納税額)の仕訳
(借方)仮受消費税 800 / (貸方)仮払消費税 400
未払消費税 400←これが消費税額
- 利益の額(売上10,000-仕入5,000=5,000)
<税込み処理の場合>
- 仕入れ時の仕訳
(借方)仕 入 5,400 / (貸方) 現 金 5,400
- 販売時の仕訳
(借方)現金 10,800 / (貸方) 売 上 10,800
- 決算(消費税納税額)の仕訳
(借方)租税公課 400 / (貸方)未払消費税 400
- 利益の額(売上10,800-仕入5,400=5,400)
以上のようになります。
税込み処理でも税抜き処理でも仕訳の仕方の違いだけなので、消費税額は変わっていないことが分かります。
しかし売上高や仕入高が変わってくるので、利益額も変わることになります。
消費税の処理での注意点
消費税の場合は、中間申告・中間納付がありますので、それらの対象になっている場合はさらに注意が必要です。
例えば、11,000円中間納付して、決算になってみたら消費税額が20,000円だった場合の経理処理を見てみましょう。(税込み方式)
- 中間納付時の処理
(借方) 租税公課 11,000 / (貸方) 現金11,000
- 決算時(20,000円のうちすでに中間納付で11,000円支払っているので、不足分は9,000円となる)
(借方) 租税公課 9,000 / (貸方) 未払消費税9,000
これらに注意して仕訳を行ってみてください。
まとめ
ここまで「会社設立したり法人成りしたりした場合(法人化した場合)の消費税」について、様々な角度から見てきました。
まず「消費税の免除」だけを目的にしないでください。
法人化することで、最長2年間は消費全が免除されるというメリットがありました。
しかし説明したように最長2年ですので、その後はそのメリットはありません。
会社は当然2年目以降も続いていきます。もしくは続けて行くことを求められます。
消費税の免除だけが目的で法人化することはあまり得策ではありません。
その他のメリットである「取引からの信頼性アップ」などを生かして、企業を継続していくための法人化であるべきです。
消費税の免除期間があることはメリットではあるものの、その他の法人化する目的にプラスアルファとしてのメリットと捉えるくらいがよいのかもしれません。
また経営を軌道に乗せる時期であることを認識しましょう。
会社設立または法人成りすることは、起業のスタート地点です。
消費税の免除などを受けて資金繰りをよくする必要はあります。
しかしそれ以外にも営業面であったり、経費面であったり考えることや実行することは多くあります。
そしてこのスタート時期の行動が経営を軌道に乗せるかどうかの時期でもあります。
消費税の問題を含めてしっかりと対応をして、法人としてよりよいスタートできるようにしていくべきだと思います。
法人として軌道に乗せて行くのに今回の消費税の話などをぜひ役立ててください。