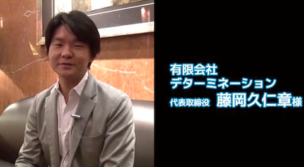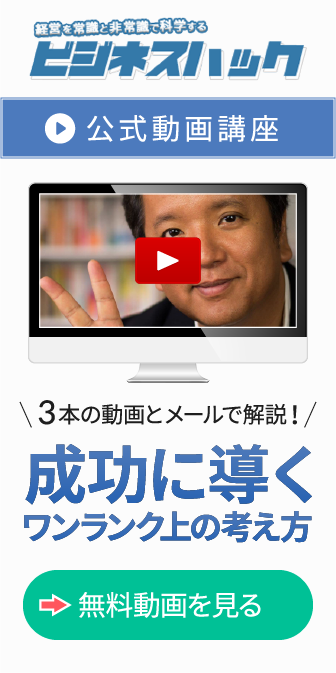ライフタイムバリューと顧客視点で売上アップする方法とは?

マーケティングでは、売上を伸ばすには、「顧客の視点」が必要だと言われるようになってきています。
では、顧客の視点とは何なのでしょうか?
顧客の視点と言っても、様々な見方があるはずです。
その中でも、今回は、ライフタイムバリュー(LTV)と言う見方を説明していきます。
このライフタイムバリューを知ることによって、売上を最大化するだけでなく、今まで見落としていた視点(機会損失をしていた視点)に気付くことも出来るようになります。
また、ライフタイムバリューは、インターネット通販などで良くつかわれる言葉ですが、一般の企業での顧客接点の視点としても重要なものです。
今回はこの「ライフタイムバリューとはどんなものか?」から始めて、「ライフタイムバリューの計算方法」や「ライフタイムバリューの使い方」まで説明していきます。
ぜひライフタイムバリューと言う視点をもってマーケティングに取り組むためにも、ライフタイムバリューとはどんなものかを知って、ビジネスの向上に役立ててください。
ライフタイムバリューとは何なのか?
ライフタイムバリューとは、「顧客生涯価値」とも言われます。
顧客から自社がどのくらい価値を得ているかという視点になります。
企業の業績は顧客から得るものですので、これを知っているのと知らないままでは大きな違いが出てきます。
そもそもライフタイムバリューとは、どのようなものなのか?
ライフタイムバリューとは「顧客生涯価値」と言われ、企業がその顧客からどのくらいの価値を得るかを示すものとなります。
しかも「生涯価値」といっているように、一回当たりの価値ではなく、生涯にわたっての長期的な価値を計算します。
例えば、「300円で仕入れた商品を1,000円で販売しました。」と言っても、1回しか買わない人もいれば、何度も買ってくれる人もいます。
単に損益計算だけをするのであれば、どちらも売上・利益は一緒です。
しかし長期的な視点で見れば、その顧客から得る売上や利益は全く違います。
もちろん何度も買ってくれる人の方が売上や利益は多くなります。そこで顧客生涯価値を知っておく必要があるのです。
ライフタイムバリューを知らないと(活用しないと)どうなるのか?
ライフタイムバリューを知っている場合と知らない場合ではどのように違いのでしょうか?
昔からリピートしてくれる顧客は、企業にとって良い顧客だと言われます。
あくまで「経験則」や「気持ちの問題」でしかなかったはずです。
しかしライフタイムバリューを計算することによって、リピートする顧客の方が企業に価値を置く与えることが数値としても分かるようになってきました。
逆にライフタイムバリューを知らないままでは、目先の売上や利益を追い求めてしまい、長期的な視点が欠如してしまうことになります。
これでは長期的に売上や利益が低迷しかねません。
ライフタイムバリューを知って、それを活用することは、ビジネスにとって重要度が高いのです。
ライフタイムバリューの重要性
リピート顧客が大切だという話は昔からあり、「いまさらそんなことを聞かなくても大丈夫」と思う方もいるかもしれません。
しかしライフタイムバリューは、リピート顧客が大切というだけにとどまらず、計算をしてどこくらい顧客生涯価値なのかをはっきりさせることができます。
これがはっきりさせることによって、
- 「どのくらい広告費をかけるべきか」
- 「売上を伸ばすには、どこに力を入れるべきか」
などが具体的に分かることになります。
今までは経験則などで行っていたマーケティングを、より具体的に、より正確に行えることになるのです。
ライフタイムバリューの基本とは?
ライフタイムバリューの基本的な考え方
ライフタイムバリューは、意外と最近になって出てきた考え方です。
ダイレクトマーティングがひろまることによって、顧客生涯価値が注目されるようになったからです。
ライフタイムバリューと聞くと、インターネットビジネスだけの考え方のように感じる方もいるかもしれませんが、リアルなマーケティングでも同様に重要度が高い考え方です。
ライフタイムバリューは、まずはライフタイムバリューを知る(計算する)ことによって長期的な売上や利益が分かるだけでなく、どのくらい広告費をかけることができるかまで計算することが出来ます。
これによって広告費を過不足なくかけることでき、赤字になったり、機械損失をしたりすることを回避することが出来るようになります。
ライフタイムバリューの計算式の基本とは?
ライフタイムバリューは計算が出来ます。
基本的な計算式は、
「ライフタイムバリュー=顧客の購買単価×リピート数」
です。
事例1
例えば「Aさんは、1個1,000円の商品を10回購入する」となれば計算式は、「1,000円×10回」となり、ライフタイムバリューは10,000円です。
言い換えるとAさんが企業にもたらす価値は、1回あたりは1,000円ですが、生涯価値では10,000円と言うことになります。
上記はかなり単純化していますので、業種によってはもう少し詳細な計算式になっていきます。
事例2
例えば「ある美容室の顧客単価が5,000円。年4回来店し、それが10年続く」のであれば、「ライフタイムバリュー=顧客の購入単価×顧客の購入頻度×継続期間」と言う計算式で計算されます。
「5,000円×4回×10年」となり、ライフタイムバリューは、200,000円となります。
事例3
ライフタイムバリューはインターネット通販で良く使われる言葉ですので、化粧品の定期購入をインターネット通販で販売している会社で見てみましょう。
「顧客は購買単価の平均は10,000円です。これを毎月定期購入しています。しかし定期購入を解約する人も出てきます。解約する人を考慮すると、継続期間の平均が2年と計算したとします。
すると平均購入単価(10,000円)×購入頻度(12カ月)×継続期間(2年)となります。
ライフタイムバリューは240,000円です。
このように企業や業種によって若干の違いはありますが、結果として「その顧客がどれだけ企業に価値をもたらしてくれるか」を計算することには変わりありません。
ライフタイムバリューを改善する基本とは?
ライフタイムバリューは、顧客から受け取る価値の総額ですので、多ければ多いほど企業にとってはプラスになります。
単純に総額が多いというだけでなく、1回獲得した顧客から多くの価値を得るということは、新規を獲得する広告費が抑えられたり、逆に広告費をかければ売上が伸びやすい状態だったりと良いこと尽くめなのです。
企業にとってライフタイムバリューを改善することは、企業業績アップに直接関わることになります。
ではどのように改善すればよいのでしょうか?
ライフタイムバリューの計算式を思い出してください。「平均顧客単価×購入頻度×継続期間」です。
これらを改善すればよいのです。
前節の化粧品のインターネット通販で言えば、
- 「違う種類の化粧品も併せて販売するなどの平均顧客単価を上げる」
- 「新たな使い方を提案するなどして使う回数を増やしてもらい購買頻度を上げる(1ヶ月に1回の購入を1ヶ月に2回の購入に促す)」
- 「アフターサービスをしっかり行い継続期間を伸ばす」などが考えられます。
このように
- 「平均顧客単価」
- 「購買頻度」
- 「継続期間」
のいずれかを改善(または、2つか3つを改善)すれば、ライフタイムバリューも改善できることになります。
注意点としては1つを改善しようとして、他が悪化しては意味はありません。
例えば平均顧客単価を上げようとして、それ以上に購買頻度や継続期間が下がってしまい全体として改善にならない(またはマイナスになる)と言うことは避けるべきです。
ライフタイムバリューをどのように生かすのか?
インターネットでのライフタイムバリュー
ではインターネットでライフタイムバリューを生かすにはどのようにしていくのでしょうか?
ライフタイムバリューをより良くしていけば企業に業績が伸びていきます。
しかしライフタイムバリューの生かし方は、それだけではありません。
インターネットで商品を販売する時には、インターネット広告を使うことになります。
その時に赤字になるような広告費のかけ方はできませんので、利益が出るように広告費を投入することになります。
その時に顧客を獲得する単価が分かっていれば、それまでは広告費をかけても赤字にならないと変わります。
これを顧客獲得単価(CPA)と言います。
その顧客獲得単価を計算する時にライフタイムバリューが必要となるのです。
例えば商品1,000円を販売した時に、この粗利益が400円(粗利益率40パーセント)の場合、400円までは広告費をかけても赤字にはなりません。
「単価×粗利益率=目標顧客獲得単価(目標CPA)」となります。
この場合、400円となります。
しかし上記までで見て来たように、顧客は一回だけしか購入しないのでなく、リピートをします。
そのリピートも考慮すべきなので、「顧客生涯価値(ライタイムバリュー)×粗利益率=目標顧客獲得単価(目標CPA)となります。
上記の例でいうと、単価が1,000円だとしても年間購買頻度が12回で、継続年数が2年であれば、ライフタイムバリューは24,000円です。
それに粗利益率40パーセントをかければ、9,600円となります。
つまり1回だけで見た場合と、ライフタイムバリューを考慮した場合では、許容できる広告費にかなり違いが出ます。
ライフタイムバリューを把握しているかどうかで、その後の成長度合いが変わります。
また逆に見方をすれば、リピートをしてもらえるように力を入れることで、ライフタイムバリューが改善され、さらに広告費を投入できる額が増えるので、さらに売上も伸び得るという好循環が生まれます。
BtoCでのライフタイムバリューとは?
リアルビジネスでは、
- BtoC(一般顧客向けのビジネス)
- BtoB(企業向けのビジネス)
がありますが、BtoCビジネスでのライフタイムバリューを見ていきます。
インターネットでのビジネスでも、広告費を使うようにリアルのBtoCのビジネスでも広告費を使います。
例えば飲食店が新聞の折り込み広告を使う場合などです。
居酒屋さんで
- 顧客の平均が単価2,000円
- 年に2回来店
- 3年継続している
ということが分かっていれば、ライフタイムバリュー(2,000円×2回×3年=12,000円)が分かります。
粗利益率が30%とすれば、目標CPAは4,000円となります。
飲食店などでは「リピート顧客は大事」と昔から言われますがこれらの数値を見ても、リピートが多いほど広告にかける費用も多くできるので、さらなる売上が期待できるのです。
BtoBでのライフタイムバリューとは?
インターネットでのビジネスでも、リアルビジネスでも、なんとなくBtoCではライフタイムバリューを活用するイメージはしやすいと思いますが、企業対象のビジネスでは、どのように活用するのでしょうか?
BtoBでも、リピートを促した方がよい商品やサービスであれば、ライフタイムバリューは活用できます。
例えば税理士やコンサルタントのようなサービスを企業に向けて提供している会社では、ライフタイムバリューが高い方(リピート率が高い方)が、新規の顧客を獲得しなくてもよいということになります。
また商品の販売をするにしても同様です。
例えば文房具などの消耗品を販売する場合でも、継続的に購入してもらえるなら、ライフタイムバリューが高くなり、その分新規獲得の費用が少なくて済むので、商品を安く提供でき、さらに継続できると言う好循環が生まれます。
逆にライフタイムバリューの視点が無いと、サービスや商品の価格決定や新規獲得に悪影響を及ぼすことになります。
このようにBtoBでもリピートするような商品やサービスであれば、ライフタイムバリューを把握することは、業績に直結していくことになるのです。
ライフタイムバリュー事例1
インターネット通販での健康食品の事例を紹介します。
健康食品などはインターネット広告も使いますが、テレビCMや新聞広告など積極的に広告費を使っている企業が多くあります。
これはライフタイムバリューをしっかりと把握できるからこそできることです。
1回だけの販売では数千円の単価の商品を、販売をしてもテレビCMなどに多額の費用をかけていては、費用対効果は出ないはずです。
しかしリピートまで考慮してライフタイムバリューを把握していることで、広告費をかけても利益が出るようなビジネスモデルになっているのです。
このような健康食品の場合でも、ライフタイムバリューを改善していく努力をしていきます。
まず商品単価を上げることを考えるのですが、ここは競争が激しくて、そう簡単ではありません。
そこで次に考えるのは購入頻度を高めることと継続期間を長くすることです。
最近の通販会社は顧客のフォローがしっかりとしています。
それは商品が1回売れればよいわけでなく、リピート(購入頻度や継続期間)が大切だと分かっているからです。
オペレーターは単に注文を取るだけでなく、顧客とのコミュニケーションまで大事にします。
それによって
- その企業への親近感がわくことにもなる
- 会話の中で商品の使い方について提案できる
- 何らかの不安や不満を聞いてそれを早めに解消したりできる
ことによって、購入頻度や継続期間の改善していくのです。
顧客のフォローをしっかりし顧客の満足度を高めることには、ライフタイムバリューを高めることになり、次にはさらになる広告費を出せることになり、結局は企業の業績にも良い影響を与えることになるのです。
ライフタイムバリューの事例2
事例はリアルビジネスでの事例です。
美容室の集客手段はホームページなどのインターネット広告もありますが、地域の情報が掲載されたフリーペーパーの公告に頼るところが大きいです。
ここで問題はフリーペーパーからの集客は多いものの、同じ紙面に掲載される競合他社も多く10%オフや20%オフなどの価格を下げて集客せざる得ないことです。
さらにフリーペーパーから来店した顧客をリピートにつなげることを意識していないことが多い点も問題です。
これはライフタイムバリューと言う視点が、乏しいと新規顧客角とばかりに目が行って、リピートの大切さを理解していないからです。
例えば
- 広告費が10万円
- カット、カラーなどの平均単価10,000円
とします。
ライフタイムバリューの改善を意識せず、新規ばかり考えていたら、単純計算で毎月10件は新規を維持しないといけません。
しかしこれが新規顧客の2回目の来店を促すことや数回、来店した顧客に対して継続して来店してくれるような仕組みを作ることで、ライフタイムバリューを改善できます。
そうすればリピートの顧客だけで店舗を維持でき、広告費がいらなくなります。
別の見方をすればリピートだけで店舗が維持出来ているうえで、広告費をかければ、さらに売上が伸びるということになるのです。
このようにライフタイムバリューを知るだけでなく、改善策につなげることによって(活用することによって)、業績アップに寄与することができるのです。
まとめ
昔から「リピート顧客を大切にしたほうがよい」と言われてきたものの、あくまで経験則・感覚の世界でした。
しかしライフタイムバリューを計算することにより、リピート顧客の大切さが理解されました。
さらに
- 広告費をどのくらい
- どのように掛けるか
という、積極的なマーケティングにも活用され、企業業績にも直結していくことになります。
またインターネット広告だけでなく、リアルビジネスでも活用できることは、事例などを見ても明らかです。
ライフタイムバリューは、
- 「意味を理解していればよい」
- 「計算式を知って計算ができればよい」
と言うものではありません。
意味を知り計算をして、さらにそれを生かさなければ意味はありません。
マーケティングと言うと捉える方によっては、「顧客をだまして、物を売る」と言うイメージもあるかもしれません。
しかし本来マーケティングは、「良い商品であるにも関わらず、顧客に伝わっていないので、売れない物をマーケティングを使って伝えて売る」と言うものです。
ライフタイムバリューの考え方は企業の業績を伸ばすには、「リピートを増やすべき」であり、それは同時に「顧客の満足度を高めること」であることが前提です。
「顧客が満足すること」によって「企業も業績が伸びる」という両者がメリットがある関係を作ることがライフタイムバリューの根本だと考えてみてください。
ぜひライフタイムバリューを知り、活用していって顧客にも、企業に良い状態を作っていきましょう。